#Special
#Yorokobi Challenge
新規事業「エレキソルト」が 提案する新たな食体験
食品の塩味を増強させる独自の電流波形を活用した、味わいを変える製品「エレキソルト」。「キリンはこれまでお酒を含めて、楽しい食卓を支えようと頑張ってきました。エレキソルトも形は違えど、食卓を楽しくするという点では変わらないと思っています」
そう語るヘルスサイエンス事業部の佐藤愛は、キリングループ全体から広くビジネスアイデアを公募し、社員のチャレンジを支援する「キリンビジネスチャレンジ」を経て、エレキソルトを事業化。エレキソルトの開発者の佐藤に「エレキソルトのある未来」の話を聞きました。

-
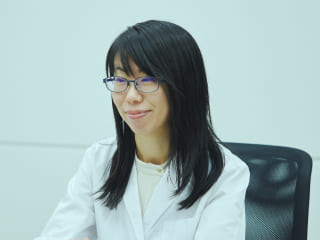
佐藤 愛
キリンホールディングス
株式会社ヘルスサイエンス事業本部
ヘルスサイエンス事業部
新規事業グループ2010年キリンホールディングスに入社し、研究開発および企画業務に従事。2019年、明治大学 宮下芳明研究室と共同で「エレキソルト」の前身となる技術を開発。同年「キリンビジネスチャレンジ2019」に応募して、2020年よりエレキソルトプロジェクトを発足させ現在に至る。
2010年キリンホールディングスに入社し、研究開発および企画業務に従事。2019年、明治大学 宮下芳明研究室と共同で「エレキソルト」の前身となる技術を開発。同年「キリンビジネスチャレンジ2019」に応募して、2020年よりエレキソルトプロジェクトを発足させ現在に至る。
※所属は取材当時のものであり、現在の組織名と異なる場合があります。
舌で「味の成分」をより感じやすくして、 料理の印象を変える
舌で「味の成分」をより感じや すくして、料理の印象を変える

-
─まずはエレキソルトを使うと、なぜ塩味を感じやすくなるのでしょうか?
佐藤:エレキソルトは、微弱な電気を使って食品中の「味の成分の動き」をコントロールする技術が搭載されたデバイスです。食事に含まれる塩分やうま味といった味の成分は「イオン」と呼ばれる電気的な性質を持っています。
独自の電流波形を持つ電気を流すことにより、イオンの動きを制御して人間が味を感じる舌へ引き寄せていく仕組みとなっています。そのため、食品のベースの味わいを増強する役割があります。
自身も3か月間の減塩生活を体験して、 その難しさを痛感
自身も3か月間の減塩生活を 体験して、その難しさを痛感

-
─事業がスタートした経緯を教えていただけますか?
佐藤:「エレキソルト」デバイスは、KIRINと明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科の宮下芳明研究室との共同研究で開発されました。
私は2018年頃から、お客さまの健康課題を解決できるような新しい技術を探索してきました。そのなかで、健康上の理由から減塩食に取り組んでいる方たちに出会い、薄味の食事を続けることは、その方法はさまざまあっても続けること自体が難しいことを知って、根本的な解決策を見つけたいと思ったんです。
当時「食」領域の研究所に属していた私は、バーチャルリアリティの学会で宮下教授の微弱電流を活用する技術に出会いました。そして、この技術と健康課題を組み合わせることで、お客さまの苦しみを解消できるのではないかと考え、共同研究を提案させていただきました。
そして2019年から共同研究を開始しました。KIRINの研究員が持つ「業務時間の10%を業務外の探索や研究に使える」というルールを活用し、まずは手作りの機械で実験をスタートさせました。共同研究だけに契約やお金も必要でしたが、研究所長に仲間になってもらったり、上層部にもプレゼンしてご理解をいただいたりしながら、プロジェクトを進めていきました。

-
─それだけプロジェクトに情熱を注げたのは、何か理由があったのでしょうか。
佐藤:二つの原動力があります。一つ目は、減塩が必要なお客さまからお話を直接うかがって、その辛さを実感したことです。私自身も3か月間、食塩相当量を1日6グラム未満に控える減塩生活を体験してみたのですが、次第に食の楽しさが失われていくようで、毎食続けることの難しさを痛感しました。
二つ目は、私はもともと「食」の研究をする一方で、バーチャルリアリティなど別分野の技術にも興味を持っていました。「技術の掛け合わせ」で新しい何かが生まれ、社会実装できる期待感があったんです。私にとっては技術者としての大きなおもしろみでもあり、エレキソルトを事業化する熱意が高まった理由でしたね。
いつもの食器のように使えて、 日常に溶け込みやすくするために
いつもの食器のように使えて、 日常に溶け込みやすく するために
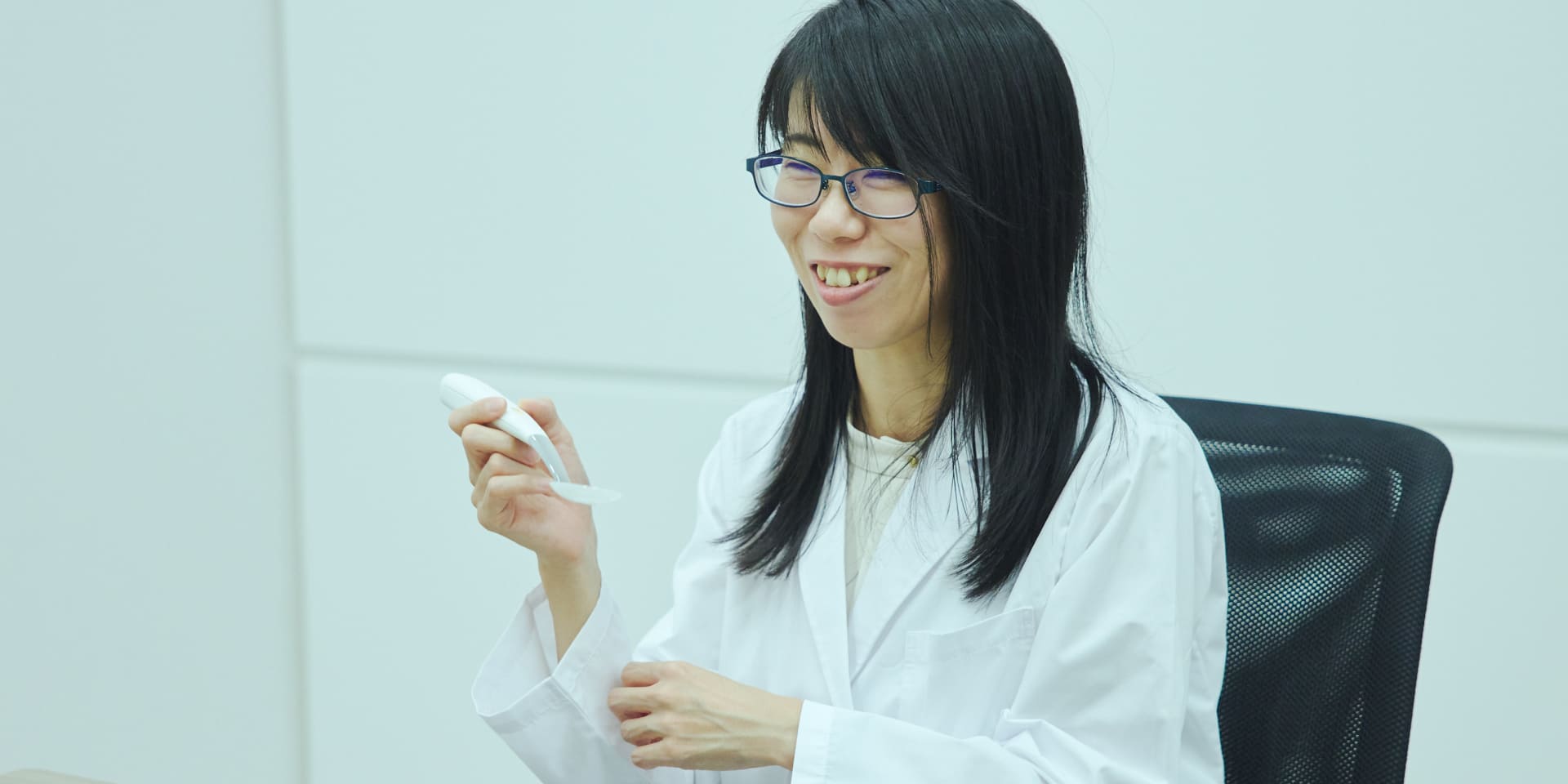
-
─現状では、どのようなお客さまを想定していますか。
佐藤:まずは実際に減塩が必要な方に食事をより楽しんでもらうことが大切だと思っています。そのうえで、未病・予防くらいの段階の方々に対しても食の楽しさやおもしろさを伝えていきたいと思っています。
-
─医療機器のような形ではなく、スプーン型なのもユニークだと感じました。
佐藤:お食事の自然な動作のなかで、電気の流れを起こすためですね。エレキソルトの技術自体は、電流が食品を介して舌に流れればよいので、口や歯に装着するタイプの機器でも作用します。
ですが、普段の食事中に「特殊な機械だ」と感じずに使えたほうが、日常のなかに溶け込みやすく、浸透しやすいと考えたんです。お客さまからも「身体のデリケートな問題でもあり、“何か特殊な機器を使っている人”と見られるのは避けたい」というお声もありました。
そこで、いつもの食器やカトラリーを置き換えるように使うという発想で、食卓で違和感のないように見た目も使い勝手も極力近づける道を選びました。
キリンビジネスチャレンジで学んだ 「ビジネスの描き方」
キリンビジネスチャレンジで 学んだ「ビジネスの描き方」

-
─エレキソルトは「キリンビジネスチャレンジ」を経て事業化されましたね。参加を決めたのは、なぜですか。
佐藤:以前いた研究所でもエレキソルトの事業提案を何度かしましたが、その時点では「現業と合わないのでは?」といった意見がありました。「なぜKIRINがこれを事業にするのか」という点を私自身が十分に説明できなかったんですね。研究者として技術面での提案が中心になってしまっていて、振り返ると「社会的意義」をうまく説明できていなかったと思います。
事業化前に学会で発表した際に、あるテレビ局の方が「社会的意義があって取り上げたいが、メディアへの露出の仕方を誤るとよくない伝わり方をしかねない」とアドバイスをくださったんです。
そこで、関係者で話し合って社会的意義を中心に据えた番組構成にしたところ、お客さまからも「生活が変わる」という期待の声をいただいて、その意義をしっかりと社内外へ伝える必要性を実感しました。
そんな経緯もあって、今後どう進めるべきかを考えたときに、「キリンビジネスチャレンジ」があることを知りました。

-
─技術者としてはいいものができそうでも、仕事の経験上としてもビジネスプランを描くのは難しかった。それが、キリンビジネスチャレンジを経て、佐藤さん自身も学びながら事業化への道が開けていったと。
佐藤:そうですね。技術にはずっと興味があって「いい製品を作れば売れる」という考えに陥りがちでしたが、事業として成長させるためには全体設計が重要だと気付きました。
そこで、他企業との連携でさらにサービスを広げることができると考え、今はほかの企業や自治体とも協力して新たな取り組みを進めているところです。
それから、キリングループとしての強みも実感しました。協業先の探索では、キリンビールやキリンビバレッジの営業部や、協和キリンの方々にもご協力いただいています。お取引先や医療機関を紹介してくださったり、医師との面談などもスムーズに進んだりするのは、やはり「KIRIN」という信頼感があってこそだとあらためて感じます。 -
─ほかの会社と協業して新しいことができるチャンスも生まれて、まさに「次のKIRINをつくる」やり方だと期待が膨らみました。一方で、「なぜKIRINが電気機器を発売するの?」という疑問も聞かれそうです。
佐藤:私自身としては、エレキソルトがKIRINから発売することには、そこまで違和感を持っていないんです。KIRINはこれまでお酒を含めて、楽しい食卓を支えようと頑張ってきました。エレキソルトも形は違えど、食卓を楽しくする点では変わらないと思っています。

-
─最後に、今後の展望についても聞かせてください。
佐藤:まずは、お客さまが期待しているものと、製品とのギャップを、しっかりと埋めていくことです。販売をスタートしてからも、お客さまや協業先からご意見をいただきながら、製品自体を改良していくつもりです。搭載している技術も、今後どんどん改良していく必要がありますから、ぜひ少し長い目で見ていただければ、と思います。
将来的には、何十年先かはわかりませんが、音楽をダウンロードするように、「味を再現するための電流の波形」をダウンロードして、それを再現して食べることができるような技術を実現できればと思っています。例えば、通信を通じて味のデータをシェアしたり、取り寄せたりできるようになるといいですよね。